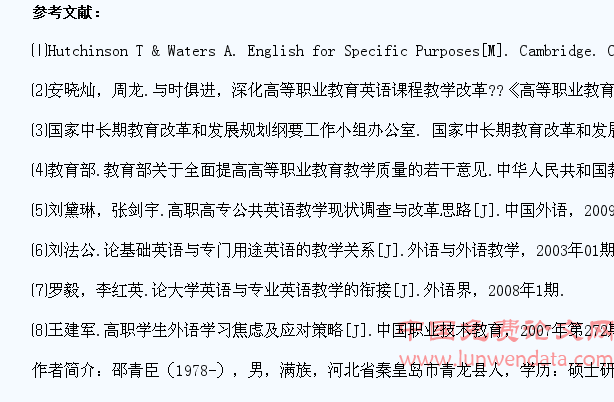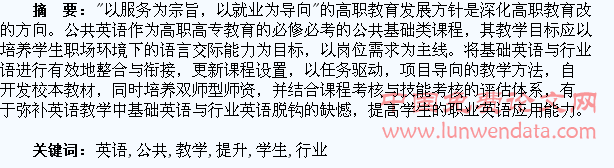2014年度河北省社会科学发展研究课题,课题编号:2014030304
1. 引言
国内外高职教育领域广泛倡导的德国“双元制”模式,其实质就是将学习任务与行业工作任务相结合。澳大利亚等国家也都非常注重职业性,强调职业技能的培养。2002年我国职业教育工作会议以来,提出了“以服务为宗旨,以就业为导向”的高职教育发展方针。2006年,教育部《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》1 中,规定要“把工学结合作为高等职业教育人才培养模式的重要切入点”,以此来突出学生职业实践能力的培养。2010年2月,教育部新出台的《2010-2020年国家中长期教育改革和发展规划纲要》2 中,明确指出现行教育模式下的弊病,提出教育改革的路线和章程:包括更新人才培养观念,创新人才培养模式,深化办学体制改革,大力发展职业教育。公共英语作为高职高专教育的必修必考的公共基础类课程,其重要性不言而喻。学好英语不仅仅是学生受到良好教育的标志,而且与学业,就业等多种学习需求息息相关。同时,公共英语教学水平也是衡量学校办学水平的重要评估指标体系。然而,国内高职院校的公共英语教学情况仍有待改善。
2. 构建基础+行业公共英语教学模式
根据教育部高等学校高职高专英语类专业教学指导委员会(以下简称“高职教指委”)于2007年进行的公共英语教学现状调查3 ,教师与学生对于教学目标的认知,教学目标认知与实际教学过程的组织,实际教学过程所体现的教学目标与学生对教学目标的理想预期之间均存在较大差距。其中就英语教学内容方面,学生普遍认为,英语教学内容应适度强化行业英语的训练。在基础英语与行业英语教学比例设置方面,认为基础英语应大于,等于,小于行业英语的比例分别为27%, 42%和31%。这说明,多数学生的共同愿望是希望学校教学能够适度强化行业英语,培养学生的职业英语应用能力。然而,在实际教学过程中,学校及教师针对行业英语教学所做的努力并不足以满足社会与学生的需求,其中,41%的高职高专院校完全没有开设有效的行业英语教学课程,有些院校即使开设此类课程,也存在着基础英语与行业英语的合理过渡与衔接问题。而另一方面,有95%的学生认为,在将来的职业岗位中,职业英语应用能力对他们的职业发展非常有用,或者或许有用。这说明,英语实际应用能力的培养,不仅是公共英语教学模式改革的基本共识,也是推动教学发展的必要手段。如何将基础英语与行业英语进行有效整合,是提升高职院校学生职业英语应用能力的有效手段,对于高职高专公共英语教学改革起到举足轻重的作用。
Hutchinson and Waters(1987)4 将外语教学分为ESP(English for Special Purposes)和GE(General English),其中ESP又可分出EAP(English for Academic Purposes)和EOP(English for Vocational Purposes), 即学术英语和行业英语。高职教指委在2009年颁发的高等职业教育英语课程教学要求(试行稿)中,提出高职类院校的公共英语教学应分为基础英语阶段与行业英语阶段,即GE和EOP的有效整合。在基础英语教学中,其主要内容为掌握英语语言共核知识(Common Core)。刘法公(2003)5 认为,语言共核是语言学家在对语言功能意念的研究中形成并提出的概念,指讲某一特定语言的人群中大多会使用的那部分语言。因此我国当前公共英语教学正是为使学生掌握语言共核而设计的。然而,行业英语则是以培养学生职场环境下的语言交际能力为目标,以岗位需求为主线,体现行业性与岗位差异,以应对不同层次的需要。
基础+行业公共英语教学模式课程培养模式,具体是指:英语基础教学+行业英语教学,在培养学生英语语言基础上,以语言共核知识为载体,提升学生职业英语能力。这就要求在教学计划中,根据社会对于高职学生职业英语应用能力的需要,针对具体的工作过程,工作的场景和任务,以岗位需求为主线,设置教学任务,实现“教、学、做”一体化。英语教师要以就业为导向,更新教学理念,根据市场需要,及时调整教学计划,多种方式组织英语教学,提高学生职业英语能力。本教学模式将公共英语课程整合为英语基础教学+职业方向,即将英语语言知识教学和行业英语应用能力培养有机结合起来,注重学生的职业英语应用能力,突出人才培养的针对性、应用性,摒弃了传统的以教师为中心,单纯传授英语理论知识的课堂教学模式,而采用以学生为中心的英语+技能的职业化教学模式,在实际操作中,积极探索任务驱动、项目导向等有利于增强学生职业英语能力。基础+行业公共英语教学模式的整合,具体来说,是课程设置,教学方法,教学内容,师资力量,评估体系五个方面的整合。
2.1 课程设置
公共英语课程的设置应以培养学生职场环境下的语言交际能力为目标,以岗位需求为主线。从当前情况看,各高职院校设置2-3学期的公共英语课程较为常见。高职院校的师生由于英语基础相对薄弱,对英语学习本身就缺乏热情。同时为了就业需要,常常把主要精力放在与英语考级相关的学习上。同时在各校英语课时日渐受到压缩的现实情况下,大多数学校根本无暇开展行业英语教学。然而根据高职教指委2007年的调查6 显示,四学期的英语课程设置最受学生欢迎,同时周四学时是最佳选择。考虑到高职院校学生英语入学水平落差较大的情况,前两学期应主要用于学生的基础英语教学,后两学期着重培养学生的英语实际应用能力及职业英语能力。 2.2 教学方法
高职教指委于2010年发布的《高等职业教育英语课程教学要求》研究报告7 中指出,针对高等职业教育学生的特点,公共英语教学应把培养兴趣作为开展教学的重要前提。王建军(2007)8 指出,目前高职院校的很多学生在英语学习方面存在情感障碍,对英语学习抱有排斥或焦虑的情绪。究其原因,还是因为学生英语基础薄弱,对英语学习失去信心。因此,在教学中应充分考虑到培养学习英语学习的兴趣。而这一目标并不是单纯通过一些趣味性的手段,而是通过借助学生对于专业知识的学习要求和兴趣,唤起学生内在的激情。
借鉴目前高职教育倡导的工学结合,工作过程导向的教学改革思路,我们在教学中采用任务驱动+项目导向的教学方法,激发学生的学习动力,使学生产生学习兴趣。在学期教学开始之前,教师应精心设计与学生专业及英语学习相关的项目,并将项目划分为若干阶段,清晰规划每次课或每几次课后学生应完成的任务。通过项目导向,建立明确的课堂规则和教学目标,给学生以安全感和成就感。通过以任务驱动,使学生不停受到外部任务的刺激,努力学习与本任务相关的当前教学内容,不至因为项目历时过久而失去动力和兴趣。在具体教学中,教师可灵活运用多种教学手段,如在基础英语教学中,结合多媒体教学手段,侧重以教师启发式讲授为基础,实现师生互动性教学,如角色扮演,情境模仿等。而在行业英语教学中,则可以结合项目设置,为学生提供英语实训环境,通过“教,学,做”为一体的教学模式,切实提高学生的职业英语应用能力。
2.3 教学内容
高职高专院校公共英语教学内容的选择,应该依据是否能最优化提高学生的职业英语应用能力为目标。由于行业英语开展时间较短,我国高职院校专业设置灵活多样,加之各校实际发展中对各专业侧重与教学目标并不统一,当前涉及基础英语与行业英语整合教学的教材良莠不齐。因此我们在教学中结合学生各专业教学内容情况,参考现有行业英语教材内容,在课程专家的参与下,自主开发教学材料。教学内容的开发应注意两个方面,一是行业英语在基础英语中的全过程渗透,即在前两学期的基础英语教学中,教师应以共核心知识为桥梁,以专业英语词汇为载体,向学生渗透专业英语的教学内容。第二个方面是基础英语与行业英语的自然过渡,即在后两学期的行业英语教学中,也不应完全摒弃基础英语的巩固和提高,实现两者的有机结合。
2.4 师资力量
根据调查,在我国当前为数不多的开展行业英语的高职高专类院校中,行业英语大多由专业教师担任。然而罗毅等(2008)9 认为,ESP教学应理解为把专业作为载体的一种教学理念,其教学内容侧重英语,目的是帮学生掌握某一专业领域的语言特征。作为ESP的一个分支,考虑到英语教师更加擅长语言学与教学法的实际,我们认为行业英语教学应由英语教师担任。但另一方面,英语教师缺乏学科领域知识的现实,因此师资力量的问题亟待解决。提高教师专业化水平,可通过以下途径进行,如选派行业英语教师参加有利于行业英语教学的师资培训,派驻行业英语教师到相关企业公司进行锻炼学习,与专业英语教师进行定期学习和交流,参与行业英语教学的实践研究以及教师的自主学习。建立具有专业化水平的行业英语教师团队,是当前基础英语与行业英语整合中亟待解决的问题。
2.5 评估体系
有效的教学评估体系对于教学能够起到积极的反拨作用,而不当的评估方式也会影响教学课程的设置与实施。当前高职院校中,由于就业的需要,师生多把主要精力放在与考级相关的教学上,倾向于语言知识,尤其是读写能力的教学,忽略了学生的英语交际能力,更不用说职业英语能力。公共英语教学评估体系就彻底摆脱侧重英语语言知识的倾向,同时对英语实际应用能力和的形成和提高起到一定的制约作用。这就要求构建基于工作过程的评估体系,将课程考核与技能认证考核相结合。(1)课程考核均采用形成式与终结式相结合的方式,其中形成性评估占40%,终结式评估占60%。形成式评估主要以学生任务与项目的表现与完成情况为参考,从课堂活动,课外实践,作业与小组互评四个方面进行。终结式评估以学生期末成绩评定。(2)技能认证考核主要以学生A,B级成绩为参考,同时鼓励学生参加托业,托业桥等职业英语能力认证考试,并鼓励有专业认证考试的专业,如金融,IT等专业学生,参加行业英语认证考试,获取行业英语资格证书。
3. 结语
高职院校的英语课程设置必须反映职业岗位对人才的需求,体现基础+职业性特点,满足培养学生职业英语能力的需求。长期以来,高职院校的公共英语课被认为是与社会需求脱节的语言知识课,其所设置的教学内容未能与学生的就业需求相结合,因为无法满足不同工作岗位对职业英语的实际需求。将基础英语与行业英语进行有效地整合与衔接,更新课程设置,以任务驱动,项目导向的教学方法,自主开发校本教材,同时培养双师型师资,并结合课程考核与技能考核的评估体系,有助于弥补英语教学中基础英语与行业英语脱钩的缺憾,提高学生的职业英语应用能力。■注释:
1. 教育部.教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见.中华人民共和国教育部公报,2007年05期,32页.
2. 国家中长期教育改革和发展规划纲要工作小组办公室. 国家中长期教育改革和发展规划纲要.人民日报,2010年3月1日,第5版.
3. 刘黛琳,张剑宇.高职高专公共英语教学现状调查与改革思路[J].中国外语,2009年06期,78-79页.
4. Hutchinson T & Waters A. English for Specific Purposes[M]. Cambridge. Cambridge University Press, 1987.8-129页.
5. 刘法公.论基础英语与专门用途英语的教学关系[J].外语与外语教学,2003年01期,31-32页.
6. 刘黛琳,张剑宇.高职高专公共英语教学现状调查与改革思路[J].中国外语,2009年06期,80页
7. 安晓灿,周龙.与时俱进,深化高等职业教育英语课程教学改革――《高等职业教育英语课程教学要求》研究报告[J].中国外语,2010年04期,5页.
8. 王建军.高职学生外语学习焦虑及应对策略[J].中国职业技术教育,2007年第272期,16页.
9. 罗毅,李红英.论大学英语与专业英语教学的衔接[J].外语界,2008年1期,78页.