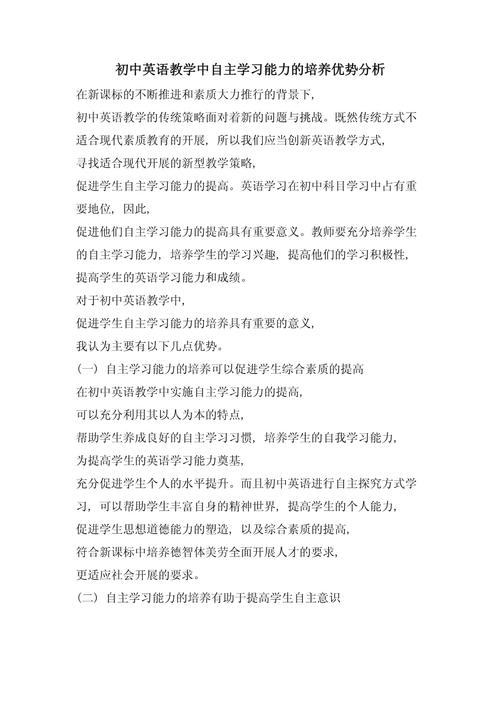
《义务教育英语课程标准》(2011版)指出:加强学习策略指导,培养学生自主学习能力。在义务教育阶段,学生逐步形成有效的学习策略对于提高学习效果十分重要。发展有效的学习策略是英语课程的重要目标之一。新课标倡导自主、合作、探究的学习方式,根据新课标要求,结合我校实际,从2012年秋季开始,我校进行了以自主学习为中心的目标教学模式的教改实验,实验率先在语、数、英三门学科展开,在取得初步成效的基础上,2014年在全校推广。2015年5月《英语教学中学生自主学习策略的研究》课题正式立项为荥阳市级课题,有了前期的工作基础,课题组对该课题迅速研究,从而达到了大面积提高教育教学质量的目的。
二、课题研究的理论依据
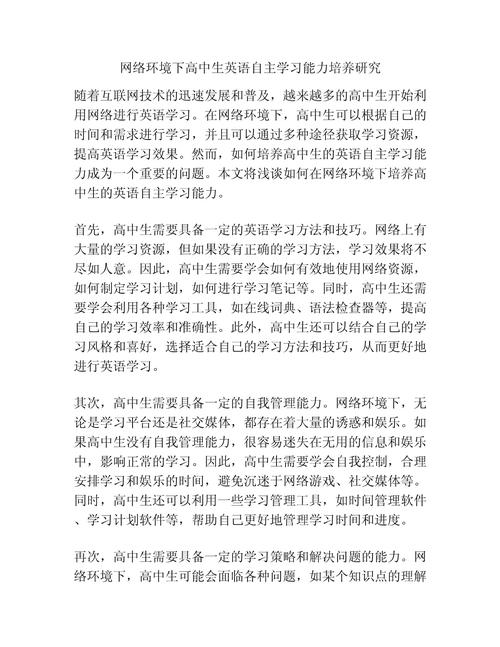
(一)教育学理论 学生是学习的主体,“教是为了不教”;培养学生的自学能力、让学生获得终身学习的技能,是教师的基本职责。让学生在自主的体验中积累知识、获取方法、发展能力,是培养学生自主学习能力的必由之路。新课标强调:加强学习策略指导,培养学生自主学习能力。新课标与教育学理论在这一观点上是一致的。
(二)建构主义者皮亚杰强调学习过程的建构性,认为“个体一出生便开始积极的从自身经验中建构个人意义、建构他对自己的理解”。建构主义教育理论认为,知识是主动建构的,而不是被动接受的,知识的意义是不能机械地灌输给学生,必须靠学生根据其个人先前知识经验主动建构。基于此基本观念,学习应由情境、协作、会话和意义建构四个要素构成。情境是意义建构的基本条件,师生、生生之间的协作与对话是意义建构的核心环节,而意义建构则是学习的目的。
三、课题研究理论假设与实验目标
自主学习能力的培养是素质教育和时代的需要,是学生健康发展的重要方面。以培养学生自主学习能力为主要目标,着眼于未来发展和学生为主体的教育思想,构建自主学习能力培养目标,探索自主学习能力形成的动因和培养自主学习能力的途径方法,培养学生良好的自主学习品质。
实验目标:
(一)发挥学生主体作用,激发学生自主探索性学习兴趣,培养学生探索知识规律的科学态度和创新精神。
(二)使学生学会运用学习策略与方法,合理调控学习过程,提高学生自主学习能力,形成良好的自我调控、自我激励、自我约束的心理品质。
(三)优化课堂教学结构,提高课堂效率,灵活运用“先学后教,当堂训练”,减轻学生课业负担。
(四)培养学生独立思考、发现问题和解决问题的能力。培养学生掌握一系列适合自己的学习方法以获取知识,以及对学习过程和学习结果进行自我检查和评定的能力。
四、课题研究的基本内容
(一)模式的基本结构:
基本环节:包括导学设疑、自学互动、释疑巩固。
基本过程:情景创设、自主学习、分组讨论、达标测试、归纳总结评价。
方法手段:学习媒体、学习素材、问题点拨、检测练习、诱导深化。
(二)操作程序与实施策略:
1. 情景创设。这是学习的心理准备阶段,旨在创境设疑、引导学习。教师根据学生的已有知识基础确定提出问题的层次与坡度,以促进学生积极主动地完成新知识的过渡与迁移。
2.自主学习。这是知识信息的传输接受与强化整合过程,旨在为学生提供生动具体的感知表象,促进学生的认知发展。教师要为学生提供充分的学习素材,充分发挥学生的自觉性、积极性、创造性。
3.分组讨论。这是认知思维的运动过程,旨在拓宽思路,培养学生的思维能力。教师根据学习目标提出问题,组织学生分组讨论,经过学生相互争辩和师生相互讨论,学生的思维实现了由具体到抽象,由感性到理性的认识飞跃。
4.达标测试。这是知识的转化、巩固和深化过程,旨在运用知识规律,促进学生智力的发展。达标练习将知识规律隐含在练习题中,让学生自己分析和解决问题。
5.归纳总结评价。这是课堂小结的空间延伸,是知识网络化和系统化的过程,旨在形成新的知识结构,同时对学生学习效果进行适时评价,反馈教学。
6.教师引导。课堂教学的全程都要发挥学生的主体作用,但每一步都离不开教师的引导。教师由知识传授者变成学生学习的组织者、引导者。
三、课题研究的实验效果与认识
(一)取得了骄人的成绩
近年来我校教师教育教学思想发生了根本性改变,业务素质有了较大提高。学校教育教学工作得到了很大程度的优化,走上了科学化、规范化的轨道。我校被授予荥阳市教科研先进单位、教育教学先进单位等荣誉称号,教改成果显著,近两年有几十名教师教科研课题获省市县奖励,教学质量大大提高,在荥阳市教研室组织的期末统考和中考中成绩年年上升,优分人数和综合排名都居全市前列,实现了全面领先、高位突破。
(二)树立了新的教育理念
我们从转变思想观念入手,采取有效措施,启发教师充分认识到由“应试教育”向“素质教育”转变的重大意义;同时我们采取“请进来、走出去”的方式,加强理论学习,召开研讨会、座谈会、外出考察等形式,组织广大教师学习,使素质教育目标教学理论深入人心。探索实践了“以自主学习为中心的目标教学模式”,使课堂教学的过程成为学生在教师指导下全程自学的过程,使学生得以生动、活泼地学习,真正成为学习的主人。
(三)锤炼了一支高素质的教师队伍
作为素质教育的主力军,教师必须具有较高的思想觉悟、专业理论水平和科学文化知识。教改实验中,突出了敬业精神、表率作用,热情鼓励和带动中青年教师学习,有计划的大练基本功,鼓励教师“一专多能”,逐步建立了一支科研、教研和骨干实验教师三结合的教师队伍。
(四)探索了自主学习目标教学基本策略
所有参与教改实验的教师都积极探索一种“引导学生学会学习”的教学理念;教学中强化“参与和竞争”两种意识;发挥“运用目标导向、加强前提评价、重视反馈矫正”的目标教学的三种优势;实施“教学组织形式、课堂教学模式、教学方法和学法指导”四项改革。实践证明,自主学习目标教学不但能够促进后进生的转化,也能使优生得到更好的发展,利于学生创新意识和实践能力的培养和提高。
(五)构建了“自主学习”目标教学模式
课题组教师在实验过程中,大胆探索建构了适合各自学生的“自主学习”目标教学模式。教学中给予学生自主学习的时空为前提,以老师全程引导下学生自己组织学习过程为核心,以促进学生自主发展为目的,它不同于平常所说的尊重学生的主体地位。各成员还能根据教学情景的变化,不断调整、更新自己的教学方法。
(六)建立完善了科学的评价机制
学校由分管校长、教导主任、教研组长和备课组长组成评价小组,查备课,深入课堂听课,参与教研活动,与教师和学生进行交流,开展各种调查活动,然后把获得的信息进行分类、归纳、总结,指出优劣在什么地方,哪些地方需要改进,哪些地方需要继续实验,并在此基础上制定出下一阶段的计划要求和标准。由于评价机制以学生的自主学习能力的培养为基础,因而大大提高了教师实施自主教学模式的动力,有利于全面发展学生自主学习的能力。
在学校的大力支持下,该课题取得了令人满意的实验成果,教师们的课改实验能力和教科研能力都大大提高。在该项实验研究的实施过程中,课题组成员撰写了大量课堂教学改革校本教研论文。成绩只代表过去,展望未来,任重道远,我们会在认真总结以往经验的基础上,继往开来,开拓进取,取人之长补己之短,深入开展课堂教学创新活动。

